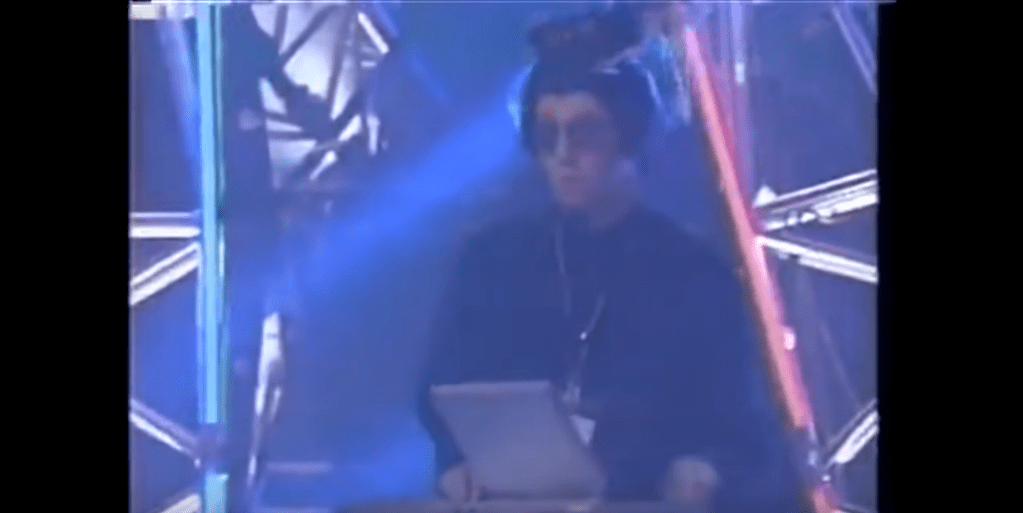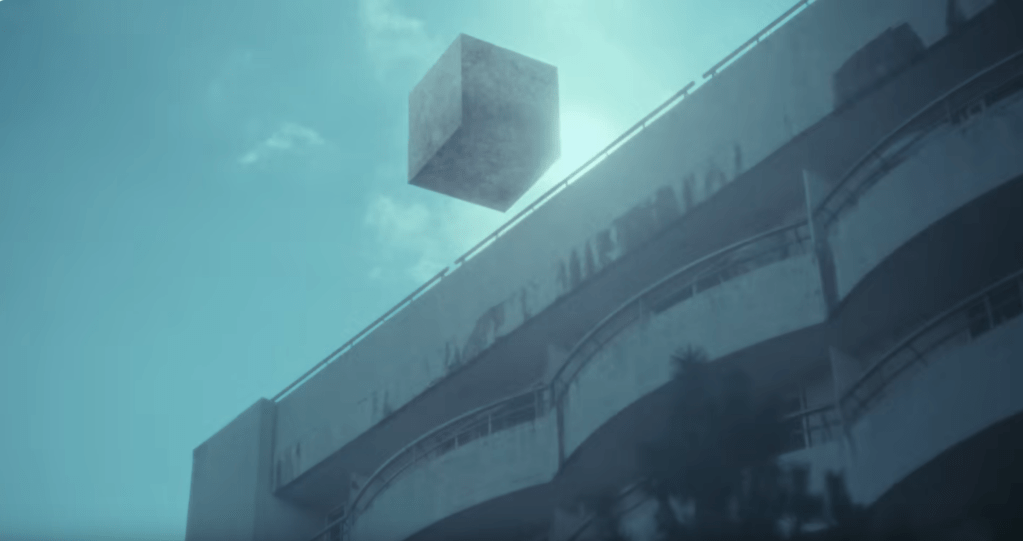毎週末の “世界の新譜” チェックは相変わらず続いており、この半年間で私が各プレイリストにラインナップする楽曲の質が大きく変化していることに、Didier PL Fanの方々はきっとお気づきだろう。
以前のPL (プレイリストの略称) に多かったチルアウトやDeep House系の音楽がグっと減り、いわゆる純粋にワールド・ミュージックと言える楽曲が増えていることに。
コロナ禍以降世界は暗闇に包まれている。政治の腐敗はもとより環境汚染による気候変動や天変地異が多発しており、創作活動がままならなくなったアーティストの話も多数聴こえて来る。
勿論此方の世界からあちらの世界への移動を余儀なくされたアーティストも多く、ただただ寂しい限りだ。


今日この記事でご紹介するのは “Une voix, six cordes – De Claude à Nougaro” と言うアルバムだ。
表現者としてYvan Cujious、そしてLouis Winsbergと言う二人のフランスのミュージシャンが表記されており、オールドスタイルのジャズ・フランセとも言うべきフレンチスタイルのジャズソングが収録されている。
全曲がClaude Nougaroの作品でまとめられている。

クロード・ヌガロと言えば、とても苦い思い出が一つだけある。
未だ私が前職で和製シャンソンの世界に深く関わっていた頃、お世話になっていたシャンソニエ “BOUM” のオーナーのご厚意でクロード・ヌガロのコンサートの (記憶では2002年だったか) チケットを手配して頂き、楽しみに会場に向かったのだが‥。
ほぼ真っ暗な照明の中にピアノ一台をバックに、クロード・ヌガロがオリジナルを歌い始めたのだがどうにも私の感性に彼の表現がフィットせず、冒頭の4曲だけを聴いて会場を飛び出した。
Pf.のモーリス・ヴァンデールのバッキングのテイストも何となくしみったれており、ほぼ暗転状態の照明の陰鬱さも手伝って私の精神の方が参ってしまいそうだったのだ。これ以上会場に居るには周囲に知り合いがあまりにも多すぎて、”拍手はしない” と言う意思表示すら難しいと思った。
後日談を聴くと皆一様に「素晴らしかった‥」としか言わない。たった一人を除いては。その “たった一人” の名前はここではあえて伏せておくが。
アルバム “Une voix, six cordes – De Claude à Nougaro” の中の一曲が丁度先週末の新譜の渦の中に登場し、先入観なく聴いていた私の心臓を一撃した。
垢抜けたヴォーカルに深い音色のギター、それらがあの、忌まわしい記憶の中のクロード・ヌガロの楽曲だと分かったが、表現や解釈によってはここまでカラっと爽やかで切れ味鋭い音楽に豹変するのかと、ある意味感動しながら今も未だアルバムを聴いている。
M-7: “Rimes” はイントロがどこかStingの “Fragile” を彷彿とさせる作りになっており、それが血の半分がアジア人の私にとっては何ともたまらない気持ちになる。
私の残りの血の何分の1がスコットランドで、残りはきっととても複雑な血が入り混じっているのだから、一体私自身のルーツの根源はどこなのかとも思うが人間なんてそんなもの。
どこかのどこかでアダムとイヴのどちらかに到達する。その先はプレアデス星人、そしてリラ星人へと辿り着くわけだから、もう誰がどこの血筋だ国籍だと訝しがること自体馬鹿げた話だ(笑)。
それにしても “Rimes” 、良い曲だ。
Rimes (歌詞)
J’aime la vie quand elle rime à quelque chose
J’aime les épines quand elles riment avec la rose
J’aimerais même la mort si j’en sais la causeRimes ou prose
J’aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche
Comme les ponts de Paris avec bateau-mouche
Et la perle des pleurs avec l’œil des bichesRimes tristes
J’aime les manèges quand ils riment avec la neige
J’aime les nains qui riment avec Blanche-Neige
Rimons rimons tous les deux
Rimons rimons si tu veux
Même si c’est pas des rimes riches
Arrimons-nous on s’en ficheJ’aime les manèges quand ils riment avec la neige
J’aime les nains qui riment avec Blanche-Neige
Rimons rimons tous les deux
Rimons rimons si tu veux
Même si c’est pas des rimes riches
Arrimons-nous on s’en fiche
J’aime la vie quand elle rime à quelque chose
J’aime les épines quand elles riment avec la rose
J’aimerais même la mort si j’en sais la causeRimes ou prose
J’aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche
Comme les ponts de Paris avec bateau-mouche
Et la perle des pleurs avec l’œil des bichesRimes tristes
J’aime les manèges quand ils riment avec la neige
J’aime les nains qui riment avec Blanche-Neige
Rimons rimons tous les deux
Rimons rimons si tu veux
Même si c’est pas des rimes riches
Arrimons-nous on s’en fiche
J’aime la vie quand elle rime à quelque chose
J’aime les épines quand elles riment avec la rose
Rimons rimons belle dame
Rimons rimons jusqu’à l’âme
Et que ma poésie
Rime à ta peau aussi…
https://genius.com/Claude-nougaro-rimes-lyrics
歌詞をめくってみると、タイトルが邦題だと『韻を踏む』と言う意味を持つ言葉だと分かる。クロード・ヌガロが元々詩人 (作詞家) として始まったことが、この歌詞からも感じ取れる。
アルバム “Une voix, six cordes – De Claude à Nougaro” のM-2: “Cécile ma fille” も、なかなかに痺れる曲だ。この曲のクロード本人の動画をあらためて視聴してみたが、どうもモーリス・ヴァンデール (Pf.) と言う人は聴衆やその時々の事情によって奏法を完全に使い分けているのではないかと、私は疑ってしまう。
勿論そういう噂を実際に聞いたこともあったが、動画を見る限り日本はPARCO劇場のあの時の演奏とは打って変わって冴えているから悔しい限りだ。
日本はPARCO劇場でのクロード・ヌガロの動画を探してみたが、見つけることが出来なかった。実際に両方のモーリス・ヴァンデール (Pf.) の演奏を聴き比べてみれば私の記憶が正しいか否か、はっきりするのだが、それは出来なかった‥。
作曲者本人よりも表現に特化して活動している面子の再演の方が原作者のそれを勝ってしまうと言う話は、よくあることだ。だがここまで歴然と表現の差を見せつけらるとは、流石のクロード・ヌガロ本人がそれを予想しただろうか‥(笑)。
ともあれ以下にアルバム “Une voix, six cordes – De Claude à Nougaro” のリンクを貼っておくので、(シャンソン嫌いの私が言うのもなんだが) 是非とも蘇ったクロード・ヌガロの世界をご堪能頂きたい。
くれぐれもこのアルバムを聴いた後に、ニッポン人のシャンソンだけは絶対に聴かない方が良いだろう。
ニッポン人のシャンソン歌手等の殆どが原作者に無断で歌詞を訳詞して、原作者に無断で楽曲を失敬して盗んで使用してカネ (ギャラ) を得ている面々だ。彼らは表現者でも歌手でもなくただの盗っ人だと私は認識しているし、このブログの読者層にもその旨肝に銘じて頂ければ幸いである ^ ^ゝ
To mark the 20th anniversary of Claude Nougaro’s death, Yvan Cujious and Louis Winsberg have decided to pay tribute to him with an album entitled “Une voix, six cordes – de Claude à Nougaro”, which revisits Claude’s incredible repertoire on guitar and vocals, a repertoire we’re more used to hearing on piano.
For this project, Yvan Cujious and Louis Winsberg surround themselves with prestigious guest friends: Francis Cabrel, Thomas Dutronc, Anne Sila, the Toulousans Bigflo and Oli, as well as great musicians like Rocky Gresset and Jean-Marie Ecay, all united by a shared love of Claude Nougaro.
This album, this wonderful adventure, is ultimately nothing more than a story of friendship, almost a family affair…
Thank you, Claude!https://www.wowhd.co.uk/yvan-cujious-1-voix-6-cordes-hommage-a-claude-nougaro/3700398731100