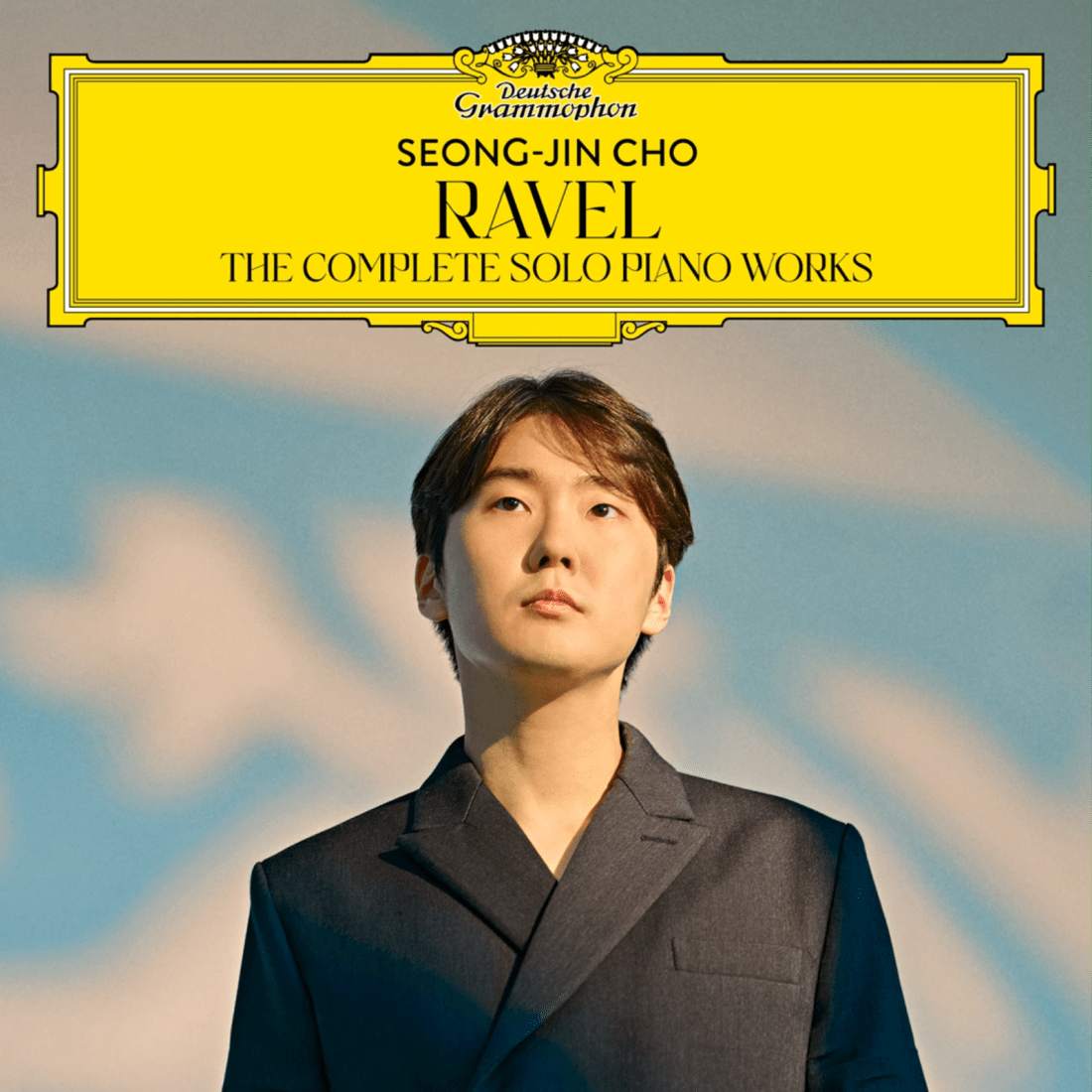そもそもの発端はSNSのXでの雑談であったが、折角の機会なのでスクリャービン (Alexandre Scriàbine) について色々深堀りしている。
書籍でも企画等でもそうであるが、一人よりは二人、二人よりは複数での研究の方が勢いづくことが多いと思うが、時に二人が一人になってしまう事故が起きる。今朝の一件がまさしく、それであった。
話をスクリャービンに戻して、先ほどから色々な演奏者のスクリャービンを聴いている。
思い起こせば私は中学生からスクリャービンを弾き始め、大学生になった頃にはクラシック界が現代音楽一色に染まりかけていた。猫も杓子も現代音楽 (特に作曲科界隈で‥) に傾倒し、調性音楽等書いている学生はどこか馬鹿にされるような空気があった。
私は破壊芸術側の現代音楽よりも、実は調性音楽側のロマン派辺りの作曲家を好んだが、周囲にそれを話したことは一度もなかった。そもそも人目に付かぬように日本のポップス界のど真ん中に陣を敷いたわけだが、それすらかなり特殊な方法で私はレコード会社各社を跨いで駆けずり回ったものだった。
話をスクリャービンに戻そう‥。
新旧色々なスクリャービンを聴いているが、どれもしっくり来ない。多くのピアニストがピアノと言う楽器の根本を、分かっていない。ピアノの打鍵の瞬間の繰り返しを音楽だと思っており、音を出さない空間を音楽として捉えていないからだろう。
だが、ピアノと言う楽器はペダリングこそがピアノらしさであり、ペダリングを制覇しなければピアノを制覇したことにはならないと、私は思っている。
特にスクリャービンの音楽はロマン派から近代音楽に跨っている為、奥底に神秘の宝がふんだんに眠っている。それはモーリス・ラヴェルやクロード・ドビュッシー、或いはセルゲイ・ラフマニノフとも異なる、もっと曖昧な雲やガスのような色合いに近い不透明性とも折り重なる感性だ。
その不透明性を表現せずして、スクリャービンを演奏することは出来ないだろう。
だが多くのピアニストに見られるのは、胸をピーーンと張って「我こそが世界最高のピアニストなり!」と聴衆を威嚇しまくるような解釈だ。
ハキハキと打鍵し、スクリャービンの持つガス感や霞のような神秘性とは真逆の表現をして、寝た子を起こすような華やかな演奏をしているように思える。リストやブラームス、ベートーヴェンじゃあるまいし、寝た子はそのまま寝かせておけば良いものを、それらの暖かなヴェールを剥がしてしまったらそれは最早スクリャービンでも何でもない別の音楽だ。
誰彼の演奏が良い/良くない‥ と言う話のテーブルのベーシックすら完成していない状態で、音楽のネタを私に振って来ること自体どうかしている(笑)。
最近のクラシック音楽界は二極化しており、かたや古典やロマン派のオーソドックスな音楽を好むリスナーと、もう片方では破壊芸術やノイズ音楽にほど近い現代音楽の側を推すリスナーとに完全に二分している。
私はそのどちらでもないからこそ、自身の音楽を生み出しているわけだが、この「どちらでもないスタンス」の方が本来の音楽の進化の方向性だった点については多くの音楽家や音楽評論家が認識していないのが現状だ。
クラシック音楽に蔓延している「聴き比べ」の文化とでも言うべきか、そこを離脱しない限り、クラシック音楽界の成長や進化は望めないだろう。
数十年も前の音源を取り沙汰してああだこうだと言ったところで、録音技術も未熟だし、何よりクラシック音楽家の権威主義が厚く業界に根を張っているような世界で、新しい価値観が芽を出す隙など無くても当然だ。
古い演奏者の音源を論評するよりも、もっと空間音響の知識を身に着けたり、クラシック音楽の分析や解釈の底板を厚くすることに注力して欲しいと願わずには居られない。
色々なスクリャービンの音源を聴いて感じることは、スクリャービン自身が望む音楽や音楽性を再現している演奏家が殆ど見当たらないことだ。
楽譜を見れば一目瞭然、スクリャービンが何を思い、どの世界観を心に持ち、その高みをどのような心境で目指していたのか‥ 等、手に取るように分かる筈。だが、そこまでの推察を施している演奏者が現状殆ど見られないことが、ただただ残念で胸が痛く、そして切ないばかりだ。
現代のクラシック音楽界の「コンクール主義」や「タレント活動」体質、或いはクラシック音楽のアンバサダー主義が演奏者及び業界の見識を完全に歪めてしまっているのだろう。
そこに付け加え、クラシック音楽愛好家の「聴き比べ主義」が業界や文化そのものを衰退させていると、私は思っている。
もしも私に弟子と言う存在があったら、何を伝えられるだろうか‥。
勿論クラシック音楽界で生き残れる手段は伝授するだろうし、既存のコンテストにも出場させることがあるかもしれない。
だがピアニストとして長く生き残るには、それだけでは足りない。
先ずは作曲を教えなければならない。そして音楽の解釈、分析をきっちりと教え込んで、最終的にはオーケストラ全体をまとめる為の手法を伝授すると思う。
その上で、自分自身の世界を持つ方法を、きっと弟子には伝授することになるだろう。

肝心のスクリャービンであるが、私は上記のミハイル・プレトニョフの演奏解釈と、本記事の最後にリンクを貼るウラディーミル・アシュケナージの解釈が好みだった。
全く余談ではあるが、スクリャービン探索の最中に色々な音楽に遭遇した。
その中で、ピダルソ (𝗣𝗶𝗱𝗮𝗹𝘀𝗼) と言うピアニストが奏でる坂本龍一の作品『A Flower is not a Flower』に息を呑んだ。
坂本龍一氏の作品の中では最も美しい曲だと、個人的に好んで色々なバージョンを聴いてもいる。
ピダルソは多分韓国のピアニスト (兼 作曲家) と思われるが、情報詳細は未だ掴み切れていない。
その動画を補足として、このブログの最後の〆に貼っておきたい。
音楽は全て繋がっている。そして時間も時空も超えて行く、とても不可思議な生命体である。
関連記事:
最後にこの記事を書く切っ掛けを与えて下さった某人へ、感謝の意を表したい。
もう二度と関わることはないかもしれないが、このような良い機会を得られたことはとても貴重な宝だったと思う。