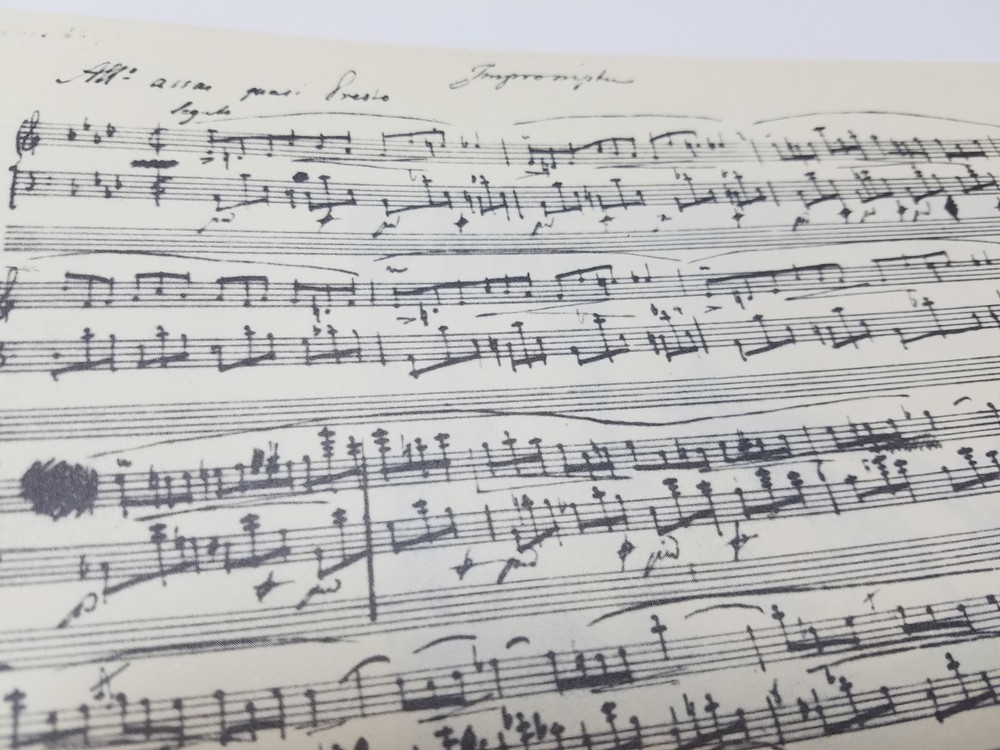【前書き】
前記事【3. ショパンの表現についての評論】では主に、ショパンのピアノ・コンツェルトを聴く時に気を付けなければならない点を含む、コンツェルトの楽曲全体を先導して行く指揮者にもスポットを当てながら解説を進めて行った。
本記事では私が今回気になった出場者5名にスポットを当て、「第18回ショパン国際ピアノコンクール」は三次予選のピアノソロの演奏に於ける各々の解釈へとさらに焦点を絞り込み、評論・解説を進めて行く。
(以上 前書きにて。)
一人目はこの人、ALEXANDER GADJIEV(アレクサンダー・ガジエフ)氏。イタリアはゴリツィア市生まれの26歳。
丁度YouTube『ALEXANDER GADJIEV – third round (18th Chopin Competition, Warsaw)』の冒頭を聴いている最中だが、特徴としてはどこか印象派の絵画のように、あえて音のアタックを不鮮明にしたところからスモークのような、柔らかく怪しい打鍵が醸し出す音色がとても印象的である。
それはどこかモネやルノワールの絵画のぼやけ感を想起させ、ロマン派からその後の近代派(スクリャビンないしはエリック・サティー)辺りの楽曲がこの人には似合うような気がして来る。
この動画の中で彼は「Shigeru Kawai」のピアノをセレクトしているが、このピアノが意外にショパンを演奏するには有利である。
中音域では「FAZIOLI」のまろやかさに似たソフト感を持ち、高音域に行くに従って「Steinway & Sons」の持つ華と「FAZIOLI」のくぐもり感の両方を兼ね備えている為、打鍵が素直に音色に反映される危ういデメリットをも併せ持つ楽器と言えるだろう。
個人的には「KAWAI」のピアノには余り好い印象を持っていないのだが、この「Shigeru Kawai」は良くも悪くも憎たらしささえ感じる。要は、うっかりすると惚れ込んでしまいそうに、所々好きな音色が浮き上がって来る‥ と言う意味で。
この難解で憎たらしい楽器をこの方 ALEXANDER GADJIEV(アレクサンダー・ガジエフ)氏は見事に使いこなしている。
逆に楽器が変わると途端に表現がゴツくなり、実際にSpotifyでリリースされている音源には正直私は余り惹かれなかった。
上の動画で特に好きだったプログラムは、Mazurkas, Op. 56/ No. 1 in B major (13:57~)。気になる方はカーソルを動かして、是非聴いてみて頂きたい。
二人目はこの人、JAKUB KUSZLIK(ポーランド出身)の演奏者。1996年12月23日生まれ、24歳。冬の神と二日違いで生まれた、文字通り見るからに神のような演奏者だ。どこか風貌が似ている(笑)。
ショパンと同じ祖国の血を持ち、ふくよかな体から生まれ出る柔らかで深みのある、ある種樹液のような深くて渋い音色が特徴だ。
この動画では若干ミスタッチも目立つが、冒頭の『Fantasy in F minor, Op. 49』の解釈は嫌いではなかった。嫌いではなかったと言うことは特に「好きでもなかった」と言う意味になるが、表現がやや短絡的でその場その場で感情が移り変わるのか、一個の世界観が持続しないのが欠点と言えるだろう。
三次予選でセレクトした楽器は「Steinway & Sons」。
オーソドックスな音色を持つピアノだが、どうにもこの楽器は何を演奏しても「Steinway & Sons」の音楽を再構築してしまうようだ。なので楽曲冒頭のインプレッションが良い分、曲が進んで行くにつれてリスナーを飽きさせてしまう欠点も併せ持っているように私は感じてならない。
だが、そんな「聴き手を飽きさせる楽器」を 、JAKUB KUSZLIK は比較的上手く使いこなしている。だが反面、彼自身の解釈のクセが段々鼻に付いて来る。
スタッカートの出し入れに特徴があり、けっしてスタッカートの音色が良くないわけではないが、兎に角クセが強いので段々と、あ~又か、あ~又あのスタッカートが来た‥ と思うと後半に向けて苛つきが生じて来る。
ここは好みの問題なので、彼のような表現スタイルを好むリスナーはさながら唐辛子の強い料理を好む人の如く、きっとたまらない演奏者だと夢中になるに違いない。
※残念ながら私はそこまで惹かれることはなさそうだ(笑)。
唯一決定的な長所を挙げるとしたら、ショパニストの多くが勘違いして身に付けてしまう「クラシック演奏家のエゴのない点」である。オレオレ、凄い俺様‥ と言う、多くのショパニストが持つ独特のエゴが全く見られないので、長時間聴いていても疲れない。
行く行くこれは彼の、大きな武器になるだろう。
三人目は二次予選の時から妙に気になっていたこの人、EVA GEVORGYAN。なんと、アルメニアとロシアの血を引く17歳の高校生だ。
17歳とは思えない舞台度胸を持ち、若さゆえの猛々しさが時折音楽のアウトラインを崩しそうにもなるが、今回の演奏では彼女の持つ「若さ」が意外にも武器になったと言って良いだろう。
良くも悪くもリベンジ能力に長けている。演奏も解釈も若い分所々で解釈の気紛れ感が音楽に小さな隙間を空けて行くのだが、その都度その度にそれを取り返すかのような表現の荒業を使ってリベンジを掛けて来る。
彼女の武器は、なんと言っても音色だろう。それもただ、女性らしい美しく柔らかい‥ と言うだけでなく、どこか数学者が奏でる「音の緻密さ」を感じさせる。ショパンも良いが、むしろ私は EVA GEVORGYAN の古典ものを聴いてみたいと思った。
ベートーヴェンやブラームス、或いはシューベルトからシューマン辺りをどんな風に演奏するのか是非聴いてみたい。
動画冒頭の楽曲『Fantasy in F minor, Op. 49』、途中からかなり派手にぶちかまして来る。若干荒さもありつつ、やはり音色に華があるので何とか楽曲のラインの乱れをそれでリカバーすることに成功している。
彼女も「Steinway & Sons」をセレクトしているが、もしかすると『Bösendorfer(ベーゼンドルファー)』が彼女の音色には合っているかもしれない。
唯一の欠点は、表情が汚い点。他の演奏家の「クラシックを演奏する時の妙な表情」を真似しているのか、楽曲の進行とは関係のない変顔が段々気になって来る。この変顔パフォーマンスの癖は、出来ればそれが体に沁み付く前に取り除いておいた方が良さそうだ。
4人目はこの人、MARTÍN GARCÍA GARCÍA。スペイン出身の24歳。24歳の割にはどこか年齢不相応の「老け感」のある演奏者だ。
お国柄がスペインと言うだけあって、舞曲にはそれなりの芯とコシと粘りを感じさせるが、兎に角演奏中のハミングが煩い。それにこの演奏者もよくある「クラシック演奏者の変顔パフォーマンス」が完全に板についてしまっており、ヴィジュアルと言う点では私は落第点を付けたくなる程気分が悪い。
パっパっパ‥ と口を鳥のように大きく開けてメロディーをなぞる辺りは、名前を出して申し訳ないが若い頃の仲道郁代さんを彷彿させるものがあり、見ている此方が段々と呼吸困難になりそうで苦しくなる。
恐らく両者の共通項として、「呼吸が浅い」か或いは「呼吸が短い」と言う致命的な欠点を持っている。一個のセンテンスが短いので、常に犬のようにはぁはぁ息が切れんばかりの浅い呼吸が癖になっているのだろう。
又、ショパンと言うよりネオ・フラメンコでも聴いているようなスパニッシュなこぶしが効いており、それを当の作曲者であるショパンは余り快く思っていないようだ。
ただ、『Sonata in B minor, Op. 58』の解釈は思ったよりは悪くない。表現に立体感があり、内旋律の際立たせ方が独特で、音楽の伏線をしっかりと出して来る辺りに表現スキルの個性と熟達さを垣間見ることが出来る。
だが如何せん変顔と歌声がもれなく付いて来るので、どうにも私はそれが気になって気になってショパンの楽曲に集中出来ない。
5人目はこの人、角野隼斗さん。千葉県出身の26歳。
私がこの演奏者を取り上げた理由は、他でもない彼の演奏がなんともクラシックには全く不向きなのに、本人が「俺様ってカッコいいぜ!」と思い込んでいる滑稽さである。
彼は既にYouTuberとして多くのファンを持つ人であるが、それが仇になっている感は否めない。
そもそもクラシックよりはロック魂の方が突出しているが、それだって本家 エリック・クラプトンと比較すると骨の髄までロック魂、ブルース魂が浸透しているわけではなく、全てが中途半端でええカッコしいの性格が「何をやっても頂点を極められない弱さ」の要因を生み出していると言える。
なまじ指が動くからか、「こんなのチョロいぜ!」と思いながらショパンを弾いているのが傍目には完全にバレているのに、本人だけがそれに気付いていない。まさに「裸の王様」のようだ。
『Mazurkas, Op. 24 / No. 4 in B flat minor』 (7:20~) の演奏も、表面的には一見上手く行っているように聴こえるが、解釈の彫りが浅く、殆ど何も考えずにひたすら身体能力を武器に弾き進めている。
ショパンが最も嫌うタイプの演奏者だ。
特にこの曲『Mazurkas, Op. 24 / No. 4 in B flat minor』は民族音楽によく見られる同主短調がふんだんに用いられており、コードで言う第三音が上下する度にエキゾチックなコード(和声)をなぞって行くが、それをここまで無頓着に弾いて平然としていられる神経の太さはある意味圧巻だ(勿論悪い意味で)。
又トップのメロディーが他の音色にかき消され、表現が平面的であっても本人はさほど気にしていないらしく、この状態だったらむしろ自動演奏で鳴らして頂いた方が聴き手の気持ちが乱れることもない。
高級ホテルのバーのBGMにゲーム音楽が流れているみたいで、本当に不快感だけが湧き出て仕方がない。不適切感きわまりない‥(笑)。
まぁ本人も職業欄に「YouTuber」と書いているので、暫くは持って生まれたルックスと恐ろしいまでの自信に支えられてそこそこ音楽業界を賑わせてくれるだろう。
後世に残る音楽家になれないであろうことは本人もきっと知っているだろうし、最初からそれを求めていないだろうから、せいぜい若いファンたちにちやほやされながらこの先そう長くはないミュージシャン・ライフを謳歌すれば良いと思う。

とまぁ長々と評論して来たが、これでもまだまだ書き足りない。
でも流石に他の演奏家の演奏を聴き続けるには体力の限界なので、本記事はここで終わりにさせて頂きたい。