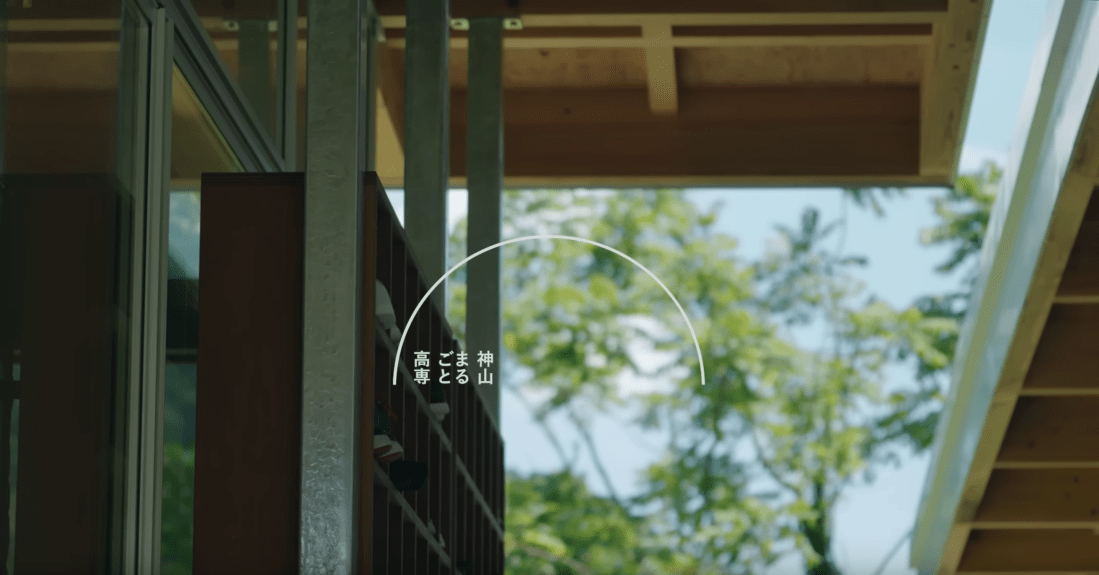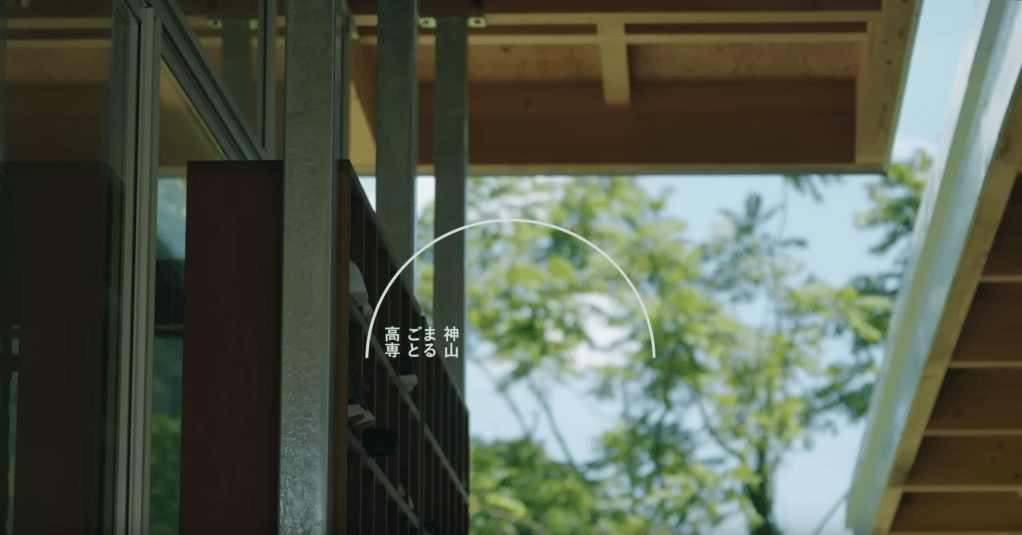昨日の明け方から少し風邪気味で、今日の夕方に開催される会食迄には治してしまいたいと思い、ずっと体を休めています。
布団の中で丸二日を過ごしているわけですがそんな中、先日更新したブログ記事『歌えない校歌「KAMIYAMA」』の閲覧者数が右肩上がりで伸び続け、大きな手応えを感じています。
『有名人の遺作として書かれた校歌だ』と言うだけで、多くのリスナーはその音楽の本質にたどり着く前に『名曲だ。』と言ってしまおうとするようです。
ジャッジメントよりも偽善の方が強くマインドを突き動かし、周囲の放つ有名税の波にあやかりたくなるのでしょう。
その一歩手前で私が先にアンチテーゼの声を上げた事は、今回の場合に於いては『吉』と出たように感じています。
中には反論や冷やかし或いは茶化しのコメントもFacebookの個人ページの記事へ複数寄せられていますが、それも『波』が立つから届く声。
反響の一つと捉え、私はただ冷静に次の波を起こすのみです。

音楽家が他の音楽家の作品をジャッジメントする事は、これまではタブーとされていました。その証拠に、自らが作品を生み出す音楽家(芸術家)たちは他者の作品に対し自身の作品でリベンジを図るのが、これまでのスタイルとされていました。
それでは何の改善も為されません。
音楽家同士の小競り合いからは、思考停止と退化しか生み出せないからです。
私が坂本龍一の作品にあえて斬り込む事には(多分これまでの業界の流れをご存知の方々もおられるとは思いますが)、他の人たちには考えも及ばない私なりの理由があります。
勿論守秘義務の範疇には触れず、いわゆる『音楽業界のディープステート』の闇を暴き出す必要性を私は今、このタイミングだからこそ痛感しています。
その意味に於いても、ブログ記事『歌えない校歌「KAMIYAMA」』の執筆は現在の音楽業界やそれを取り巻く人たちの中に、大きな一石を投じたように思います。
私自身が音楽を作り出す人間だからこそ、この記事の執筆に踏み切る事に意義があるのです。
音楽作品に対する「好き/ 嫌い」等と言う好みではなく音楽理論や世界中の全ての音楽を網羅している人間が書く文献だからこそ、大きな反響が寄せられるのです。
思うに「音楽を生み出す人々に聴衆はやたら品行方正な善人を求めたがり、それが音楽家の表現を妨害している」と、私は思います。
真実が闇の中に在るのだとしたら、音楽を生み出す音楽家たちの心の闇や「毒」にももっとスポットを当てて、それを理解するリスナー層を育成しなければなりません。

ですがそれとは逆に、例えば「校歌」の場合には、その作品には必然的に普遍性が必要になります。
「校歌」には、個性と言う名の汚れを纏わせてはいけないのです。
校歌『KAMIYAMA』に於いては、その肝心要の清潔感がゴッソリ抜け落ちてしまったようです。
それに対し、その汚れた作品性を「歌手や作詞家の個性だ云々‥ 」だと思い込ませようとするのは、ひとえにこの作品が商業作品を超えられないと言う最たる証拠を業界全体でメディアを介して露呈させている事と同じです。
本物の個性は、個性をさらに洗練させた普遍性に到達しなければなりません。
私が申し上げたいこととはつまりそういうことであり、古い体質の軍歌風の校歌を良しとする‥ と言う話ではありません。
くれぐれもそこを履き違えずに、ブログ記事『歌えない校歌「KAMIYAMA」』をあらためてお読み頂ければ幸いです。
※動画のコメント欄を見ていると、中には「歌わない校歌があっても良いではないか‥」等と言うつぶやきも幾つか見られますが、問題は坂本龍一と言うアカデミックを売りに転じた音楽家に於ける聴衆への洗脳が如何に危険であるかと言う点です。
少なくとも初演の歌手として、UAのようなタイプの歌手をセレクトしたところに大きな人選ミスが生じている点を、日本人として見過ごしてはいけないでしょう。
私ならば誰をセレクトしたでしょうか‥。
適任者がお一人おられますが、その方のお名前はここでは伏せます。
そして楽曲面で言えば、校歌がポップスであってはいけないのです。
古典音楽の楽典とコード進行をしっかり踏んだ古典的で、尚且つそれが時代を超えて行く美しさを持つものでなければなりません。
作曲者/ 坂本龍一自身、「教授」と自らを名乗らなければならなかった本当の理由を知っている筈です。彼こそ、音楽のアカデミズムを脱落し、敗北した人だからです。
ですが百歩譲って教授が校歌を作曲するのであれば、彼は最後の最後で彼自身のアカデミズムを呼び覚まし、全身全霊で校歌『KAMIYAMA』に刻印しなければなりませんでしたが、残念ながらそれは叶わなかったようです。