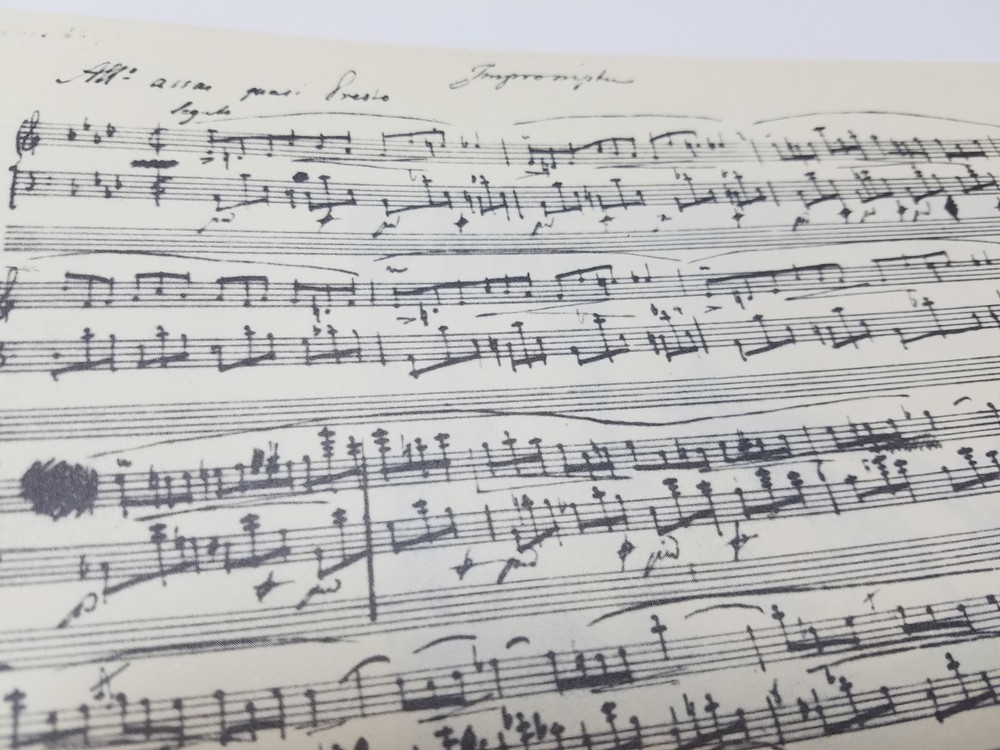【前書き】
前記事【2. アナザー・フォレスト – ショパンが本当に伝えたかったこと(表現手法・表現解釈について)】ではショパンの内面に広がる「アナザーフォレスト(天界の森)」について綴ってみたが、この記事では「第18回ショパン国際ピアノコンクール」で熱戦を繰り広げた上位入賞者が奏でたショパン・ワールドをさらに噛み砕いて評論を進めて行く。
(以上 前書きにて。)

勿論私はショパン国際ピアノコンクールの審査員ではないので、全ての出場者の演奏を聴くことは出来ないがその上で、思うところを綴って行く。
先ず本コンクールの優勝者 BRUCE (XIAOYU) LIU 氏を始めとする殆どの出場者の中に、クラシック音楽演奏者が持つ悪い癖を感じ取ることが出来る。
①自身が強調したいセンテンスになると、やたら頷いたり首を小刻みに振って自己納得するような動作が見られ、それが音楽の根幹を明らかに破壊していること。
② [①] に見られる伏線として、それがある種の内面に湧き立つ自己顕示欲或いは権威主義の顕れである点に、演奏者本人が陶酔していること。
③旋律の起伏の頂点で音符通りの到達間を「殴打するような打鍵」で、乱暴に表現していること。
④過度なエモーションが見られ、コンクールと言う設定も原因なのか‥ 多くの出場者が「闘争心」を武器に演奏していること。
以上箇条書きではあるが、今回特に私が強く感じた表現手法の間違いについて並べてみた。
他のコンクールの審査員がどうなのかについてはここではあえて問わないが、私は演奏者の力量を、例えばピアノコンツェルト等の場合には「第二楽章」で判断すべきと思っている。
これは身体能力で聴き手を圧倒すると言う姑息なトリックに騙されることなく、その演奏者自身の本当に力量や能力を嗅ぎ分けるには必要な判断スキルだと信じているからである。
BRUCE (XIAOYU) LIU 氏の場合、解釈の個性を誇張する為の「表現手法のクセ」を随所に感じる。
唯一彼の長所を挙げるとするならば、それは大所帯のオーケストラを引っ張り込んで行く力とも言えるだろう。だがこれには気を付けなければならない点がある。
先ず、BRUCE (XIAOYU) LIU 氏は完全に自分の世界に引き籠ったままショパン或いはショパンのピアノ・コンツェルトと向き合っており、指揮者の鼓動もオーケストラの呼吸も全く聴いていない。文字通り、完全に自分だけの音楽になっており、時折癇癪を起こしながら鍵盤を殴打し、その間に瞬時的に美しいパッセージも現れるがこれはあくまでピアノ「FAZIOLI」の持つ音色のマジックであり、半分以上は彼自身の音色ではないとも言える。
特に動画『final round (18th Chopin Competition, Warsaw)』(第三楽章)でのBRUCE (XIAOYU) LIU 氏の演奏は強烈に一方的であり、頻繁にオーケストラのみならず自身の演奏の上下(左右)がずれており、最早自分の演奏自体を聴いていないのではないかと疑ってしまう。
だが際限なく続くBRUCE (XIAOYU) LIU 氏の波に最後は、指揮者: ANDRZEJ BOREYKO(アンドレイ・ボレイコ)氏も呑み込まれて行く‥(笑)。
一見「コンクール」と言う会場ではこの波が武器になるかもしれないが、その後行われた入賞者の再演では見事にそれがマジックであったことが露呈した(私の耳には‥)。
ここで本コンクールをしっかりと支え抜いた指揮者: ANDRZEJ BOREYKO(アンドレイ・ボレイコ)氏に少しだけ、スポットを当ててみたい。

ポーランド人の父とロシア人の母の間に生まれたANDRZEJ BOREYKO(アンドレイ・ボレイコ)氏は、ひじょうにセンシティブで少し闇のある音楽解釈が特徴的だ。
だがそれより何より、自身の解釈を時には完全に胸に仕舞い込み、その時々の音楽の流れに疑問や葛藤に悩まされながらも最終的にはソリストである主役に音楽の結末を委ね、花を添える力には天性を感じる。
同じ演目、同じソリストにも関わらず、『final round (18th Chopin Competition, Warsaw)』と『Winners’ Concert (18th Chopin Competition, Warsaw)』とでは別の人かと思う程、表現の幅、表現の質、構成と解釈のクオリティーを完璧に変えて挑んで来る辺りに彼の指揮者としての華を垣間見ることが出来るだろう。
『Winners’ Concert (18th Chopin Competition, Warsaw)』の第三楽章の前奏からピアニストに主導権を渡して行く辺り(動画 31:40付近)に思わず、ANDRZEJ BOREYKO(アンドレイ・ボレイコ)氏は指揮者としての本領と優しさ、人間の器を見せて来るが、BRUCE (XIAOYU) LIU 氏がそれを上手く受け取ったようには見えない。
やはりBRUCE (XIAOYU) LIU 氏はここでも一方的で内向的であり、自身の内側に匿っている別のショパンを表現しているように私には視えて仕方がないのだ。
多くのリスナーはそれを「彼の個性だ」と言うかもしれないが、自身の作品ではない楽曲を表現するに辺り果たして演奏者が作り上げた第二の個性をくっつける必要があるのかと問われたら、私ならばやはり「No!」と声を大にして言うだろう。
そう、この間違った個性については他の殆どの演奏者に見られる傾向であり、中でも特に気になったのは自身を「サムライ」と位置付けている 反田恭平 氏のそれだった。
勿論自身をどうインプレッションしようが個人の自由ではあるものの、ショパンを演奏する時の主役はあくまで作曲者であるショパンであり、それ以外の演奏者がショパンを超えて主役になることは許されるべきではない。

「サムライ」と自分を名付けた割には線がふくよかで、体型と言う意味ではなく持っている彼自身の感覚の緩さ、鈍さが演奏の随所に視て取れる。
本物のサムライとはこんなものではなく常にピリピリしており、眼光が鋭く、場合によってはサングラスを装着した方が人相が穏やかに視える場合もある筈。
過去世で「忍び」を生きた私は当時何十人、何百人もの本物の「侍」と接して来たが、誰もが明日の命等補償されない危険な環境下で生きており、命を賭けて日々を戦いながら生きていた。
なのでこの人 (反田恭平 氏) に「ワタシハサムライデアル」等と言われてしまうと、此方の方が本気で刀を抜きたくなるほどの怒りが込み上げて来る‥。
それはそうと、今私は『KYOHEI SORITA – First Prize-Winners’ Concert (18th Chopin Competition, Warsaw)』に一旦動画を切り替えて聴いている。
本選ではピアノをSteinway & Sonsに指定して演奏した反田恭平氏だが、この動画では優勝者 BRUCE (XIAOYU) LIU 氏が楽器を「FAZIOLI」に指定した為だろう、反田恭平氏の「FAZIOLI」の演奏を聴くことが出来た。
それにしても何とも華のない演奏だ。
確かに誠実で真面目で、ある種の面白みのない彼の性格は一見質実剛健なショパンを繰り広げて行くが、これではプログラムにショパンをセレクトする必要性をまるで感じない。
ベートーヴェンやブラームスの方が反田恭平と言うピアニストには向いているだろう。
何度も言うが、ショパンは自身の内側に秘めた「天界の音楽」や「アナザーフォレスト」を、音楽人生の全てをかけて余すところなく書き尽くした。そのショパンの本質が反田恭平のショパンでは殆ど描かれることはなく、あくまで彼自身が思うところの「サムライ・ショパン」が粛々と弾き進められて行く。それを個性だと反田恭平氏が信じ込んでいる以上、そこにショパンの霊体が降臨することはこの先永遠に無いだろう。

再度 BRUCE (XIAOYU) LIU 氏の動画『Winners’ Concert (18th Chopin Competition, Warsaw)』に動画を戻して聴いている。
ピアノ・コンツェルトが終わり、アンコールの『Waltz in A flat major, Op. 42』を演奏しているところだが、ワルツと言うには速度が速すぎるし、何とも言えない品の無さを感じて仕方がない。
もう少し優雅に弾けないものだろうか‥。シャカシャカと先に進んでばかりではなく、例えばワツルと言う舞曲を考えたならばパートナーと共に踊り進んで行く楽曲が先ず私ならば思い浮かぶ。
女性たちならば鯨の骨が入った重いドレスを着て、髪を重く大きくてっぺんからふわりと結ってしゃなりしゃなりと踊るワルツは、もっと厳かで優雅でドレスの裾を引きずりながらゆっくりと進んで行く筈だ。
まぁこの辺りは話し出すと止まらなくなるので、追々何かの機会にYouTube辺りでお話し出来ればと思いながら、この記事を〆させて頂くことにしよう。
※今BRUCE (XIAOYU) LIU 氏の『Waltz in A flat major, Op. 42』の演奏が終わり、拍手喝さいを浴びているようだ。まるでラグビーの試合を観戦した直後のような慌ただしさと汗臭さは、本来ショパンの音楽には不要であることを最後に付け加えておきたい。