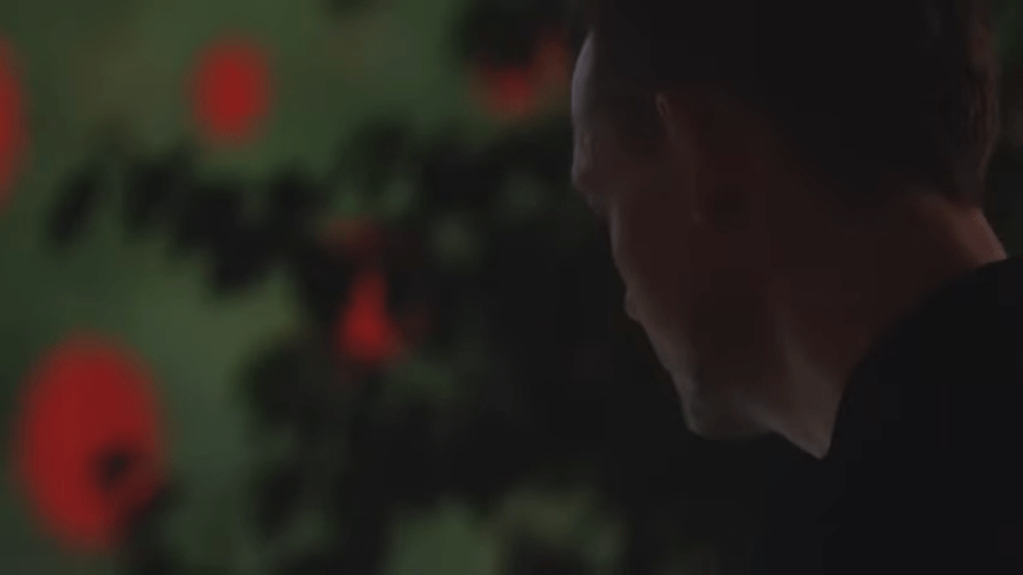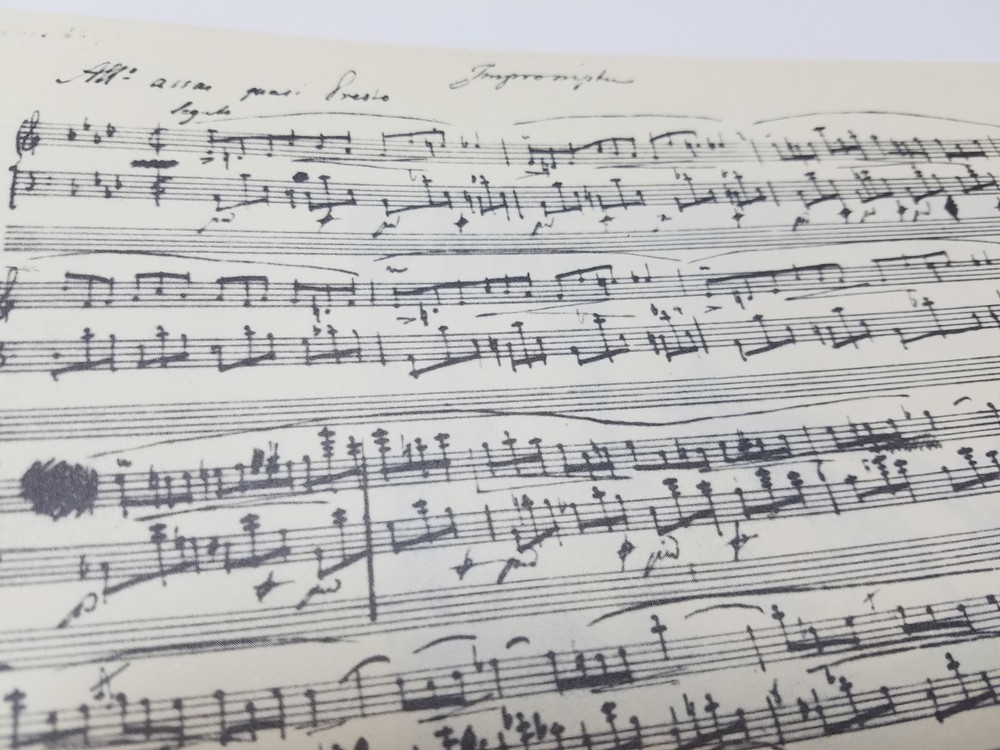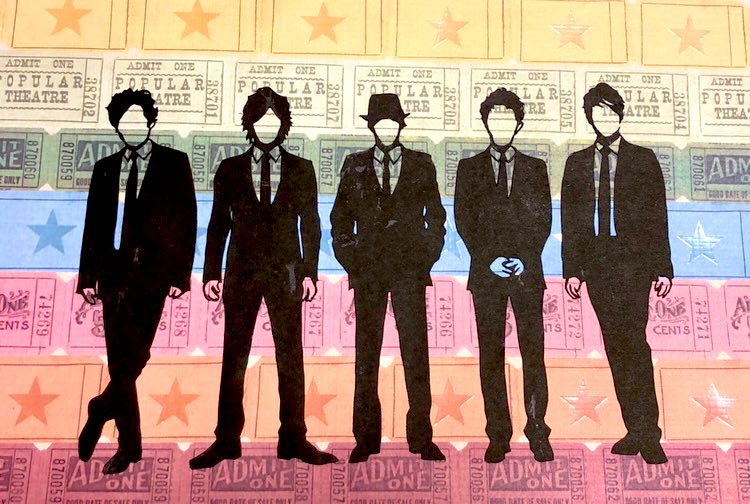「マツケンサンバⅡ」が厳密には「サンバ」ではなくマンボかルンバ‥ と言う音楽評論を目にしました。⇩
(残念ながら該当記事は2025年6月11日現在、別記事として再アップされていました。🔗画像をタップして下さい。)

音楽には色々な解釈がありますが、上記の説に於いては半分が正解であり、半分は不正解と言えます。
サンバ論或いはサンバの解釈をする際に、度々持ち出されるのが「リオのカーニバル」です。リオのカーニバルが「サンバ論」のベースとなるサンバ解釈は方々で展開されていますが、「リオのカーニバルこそがサンバである」‥ と言う視点も、あくまで規模の問題です。
基本的にリオのカーニバルの音楽(主にリズム体)の特徴として、大所帯の打楽器「バトゥカーダ」が主として16ビートの3、7、11、そして15の箇所にアクセントを感じるリズム体をキープしながら演奏されるのが特徴です。
「バトゥカーダ」は本来ヴォーカルのない音楽演奏形態を指し、主にスルド、アゴゴ、カウベル、カイシャ、アビート(ホイッスル)等と言った多くの楽器で編成が組まれ、リオのカーニバルではダンサーの後ろに大きな台車が組まれチームを鼓舞しながら会場を練り歩きます。

確かに「マツケンサンバⅡ」の原曲にはバトゥカーダ が入っていません。
元記事【マツケンサンバⅡ、正確には「マツケンマンボ」か「マツケンルンバ」?音楽学者が解説】⇦ では《マツケンサンバⅡはマンボかルンバ、ないしはキューバの音楽「モントゥーノ」かもしれない》‥ と書かれていますが、どれも正解ではありません。
ざっくりとこの音楽はシンプルに、「ラテン音楽」である‥ と言う認識の方が正しいと言えます。
少し視点を変えて、さらに説明を加えましょう。
「マツケンサンバⅡ」には複数のトラックが存在し、それぞれ個性的なアレンジが施されています。
その中で同曲が見事にサンバ・チルアウトに編曲されているのが、以下のトラックです。⇩
上記のトラックでは若干ですがリズムセクションが増幅されており、リオのカーニバルのバトゥカーダ 程ではないですが、ブラジルのサンバにかなり近づいている箇所が数カ所あります。
リズムの刻みが16ビートから、さらにかなり細かく刻む別の打楽器が背後にミックスされていて、若干付点がかった「Swing(オンダ)」を入れて打楽器がミックスされている為、リズムに空気感と躍動感が感じられます。
time 2:36 辺りから段々とSwing(オンダ)がきつくなっており、そこに「オーレ!」がリピートされている為、かなり強いサンバ感を感じることが出来ます。
よ~く聴くと、バスドラが増幅されてミックスされているので、低音部に重厚感も感じられますね。
これは「マツケンサンバⅡ」のシングルバージョンには無いアレンジになっているので、エレクトリック・サンバとして聴いたり踊ったりすることが可能です。
まぁどんなに背後に強力なリズムが来ても、上様にとっては最早どうでもいいことのようにも見えます。楽しけりゃーいいんですから、上様は!(笑)

音楽、特に『舞曲』やダンス・ミュージック、リズム・ミュージックを解釈する時に必要なことは、知識よりも感性です。
ドラムの何々が何ビートを刻んでいるから「これはサンバである」と言う数学のドリルの回答を導き出すような杓子定規な解釈は、私から見ればとても短絡的に見えます。
特に民族音楽はリズムだけではなく、そこに発祥地の「モード」や言語の特徴等が折り重なって一個の世界観を形成して行きます。なので、正しいか否か‥ を超えた音楽分析力が求められます。
元記事【マツケンサンバⅡ、正確には「マツケンマンボ」か「マツケンルンバ」?音楽学者が解説】⇦ ではどこか、マツケンブームに乗って何かしらアンチテーゼのような一家言を叩き出すことで筆者が音楽評論界に二次的な旋風を巻き起こそうとしているようにも見えます。
ですがどこか筆者の音楽解釈のツメの甘さが目立ち、多くの音楽を複合的に解釈しようとすることを拒絶しているような意図が見え隠れしている点に、個人的には問題を感じてなりません。
音楽解釈の自由性を許さない、或いは音楽を感じるマインドに余計なバイアスを掛けて行くような音楽評論は、リスナーの自由性を大きく阻害することになりますので、そのような文献にうっかり遭遇した時は出来れば余り真剣に読まずに通過することをオススメします(笑)。
さて、この記事で折角「バトゥカーダ」に触れたので、今私が個人的にイチオシの「AAINJAA」のバトゥカーダの動画を最後に置いて、記事を終わりにします。
内容を限定し、お仕事の依頼を受け付けております。
音楽評論、レビュー or ライナーノート執筆、ラジオ番組用のBGM選曲、雑誌連載執筆及びYouTube出演や対談等、諸々用件・案件は、TwitterのDMないしは 📨[info@didier-merah.jp] ⇦ までお寄せ下さい。
オーダーを遥かに上回るクールで奇想天外な記事を、筆者の豊富な脳内データから導き出して綴ります!
本記事は『note』より移動しました。